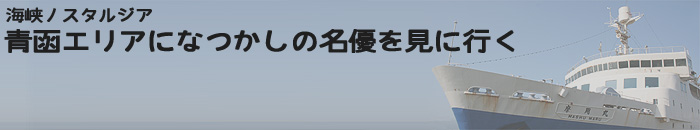
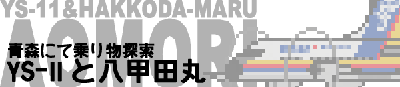
画像をクリックするとポップアップで大きな画像が表示されます。

|
いよいよ館内展示のメイン、4階航海甲板の操舵室−ブリッジへ。 広い広いブリッジは、隅から隅まで軽くダッシュ競争でもできそうなくらいの長さ。 数々の機器・装置類に息を呑むような緊張感が漂います。 |

|
操舵室のド真ん中に立って、左右を見渡すような振りをしてみれば、気分は船長さん。 実際にこの「八甲田丸」は大海原の方角を向いて停留しているので、操舵室の窓から見える風景は航海へと旅立つ瞬間の風景そのもの。 (画像では光の加減で、窓の外が白くトンじゃいました・・・) |

|
操舵室のすぐ後方には通信室。こちらもメインブリッジ同様に「船の心臓部」。 数々のメーターにスイッチがズラリ。 おびただたしい数のスイッチに囲まれた旅客機のコックピットもそうですが、それを操るパイロットや航海士って やっぱり「男の仕事」って感じで憧れますね。 |

|
ブリッジの後方から外に出ると、そこは海風が吹く「展望プロムナード」。 さらにそのプロムナードを進むと、JNRマークがデカデカと描かれた、どこからでも一番目立つ「煙突」があります。 なんと八甲田丸では「煙突展望台」があり、あの煙突に登ることができちゃいます。 |

|
まずは煙突の中に入ります。 そこには船内のいろんなところから集まった配管が巨大な4本のダクトへと集約されていました。 この4本の太いダクトがそのままてっぺんで「煙突」となって煙を吐き出すわけです。 |

|
太いダクトを避けるように設置されている階段は細く急勾配。昇りも降りる時もドキドキです。 で、煙突の一番上へ出ると・・・・そこには想像以上の絶景! まさに一面が大海原。 そこへ洋上をゆっくりと航行しているフェリーが1隻。東日本フェリーの「びるご」でした。 今回、このあと函館へ渡るのにフェリー利用も考えたのですが、時間的に合わないのと列車を使わないとフリー切符の旨みが無くなってしまうので 青函トンネルを抜けていくことにしました。 |

|
4階の航海甲板から、一気に1階の車両甲板へ。 現在保存展示されている青函連絡船で、この車両甲板を公開しているのはこの「八甲田丸」だけ。 この車両甲板の見学だけでも「八甲田丸」は訪れる価値が大いにアリ!です。 |

|
まるで迷路のように複雑に入り組んだ空間には郵便車、そしてDD16とヒ800?なる珍妙な貨車が当時の姿のままで格納されています。 この「ヒ」という貨車は、この車両甲板に貨車を積み込む際の控車。形式の「ヒ」は「ヒカエ」の「ヒ」なのかな? |

|
そしてこの車両甲板で、若干色褪せしながらも往年の存在感と美しさを誇っているのがキハ82。 実際にはキハ82がこうして連絡船に乗って、青函間を行き来する特急運用に就いていたわけではないので展示向けの架空設定なわけですが、 車両工場で落成したキハ82はきっとこうして船に乗って北海道へ渡ったのでしょうね。 



|

|
車両甲板からさらに地下1階部分へ下って行くとそこはエンジンルーム。 この巨大な船に人・荷・車・汽車を満載して、それに海を越えて行くだけのパワーを与えていたのがこのディーゼルエンジン。 照明が若干薄暗いせいか、鈍く銀光りするいくつものエンジン本体とそれを繋ぐおびただしい配線とパイプ、それに現役のままにリアルなヘコみが陰陽をつける太いダクトが この空間全体に恐ろしいまでの迫力を醸し出しています。 |

|
これで館内を一巡して「八甲田丸」見学はひととおり終了。 帰りにショップで八甲田丸や青函連絡船グッズを、どれ買おうかな・・と迷うのも見学の最後の楽しみです。 海峡を航海する“輸送機関”から、洋上文化施設としての“オブジェ”にその使命を変えて早20年。 1964年に就航した八甲田丸は、もうあと数年でメモリアルシップとして停泊し続ける時間が航海時代の時間を上回ろうとしています。 |

|
船外の周辺は公園として整備されていて、ちょうどお昼時でもあったので青森の人々が 八甲田丸をバックにお弁当を食べたり、談笑している光景が見られました。 そして船外にはもう1つ、青函連絡船の「物語」を語り継ぐ見どころがあります。 それがこの貨車の積み込みブリッジ。この角度から見ると・・・まるで何十年も前にタイムスリップしたかのような、 就航前の喧騒が聞こえてくるかのようです。 |



-SONIC RAIL GARDEN-
TOP Page TRAVELog Seat China WiLL Vi lounge SRG Link